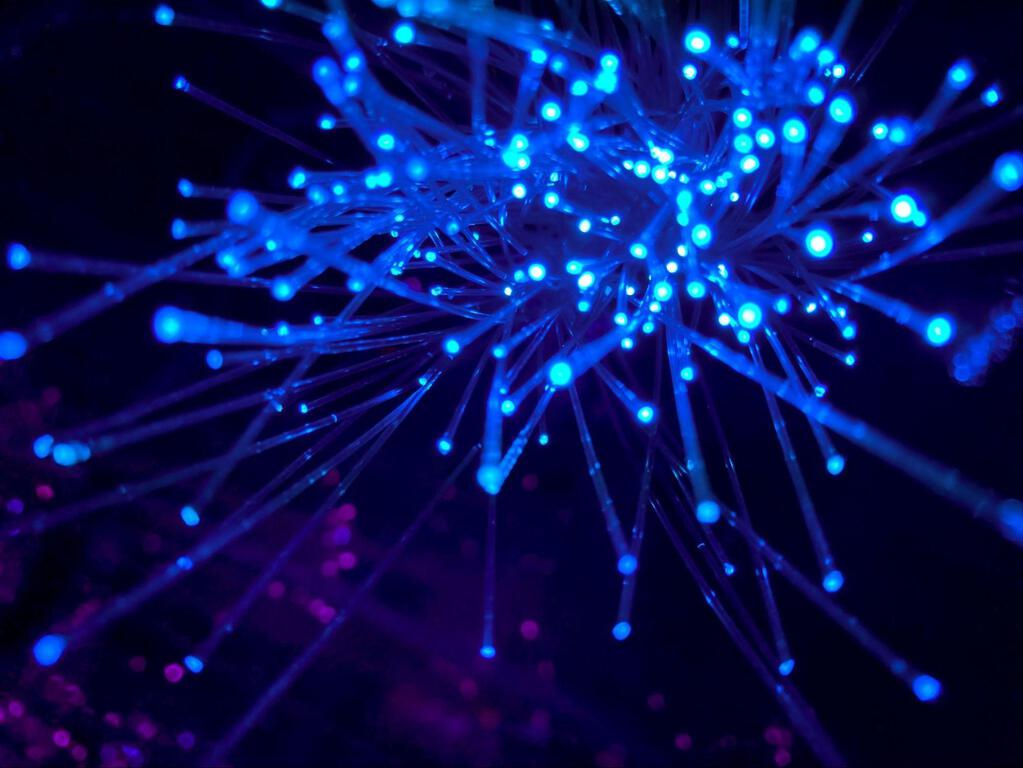RPAでできること・できないことは?自動化できる業務の考え方
業務効率化の手段として注目されているRPA(Robotic Process Automation)。定型的な作業を自動化し、人的ミスの削減や生産性向上に役立つツールですが、実際にどのような業務を任せられるのか、そしてどのような業務には向いていないのかを正しく理解することが導入成功の鍵となります。
本記事では、請求書処理や入金確認といった代表的な「RPAでできること」の具体例から、不得意とされる作業、自動化に適した業務を見極めるための考え方まで詳しく解説します。自社にRPAを導入する際の参考にしてください。
目次
- 1. RPAができることの具体例
- 2. 請求書作成業務
- 3. 口コミ・価格調査
- 4. 発注リスト転記業務
- 5. 勤怠管理
- 6. 顧客情報のシステム登録
- 7. 問い合わせ対応
- 8. 入金確認業務
- 9. RPAができないこと
- 10. 自ら考えて判断すること
- 11. ルール変更が多く複雑な作業
- 12. 手書き文字や画像の解析
- 13. RPAで自動化できる業務の考え方
- 14. ルールが頻繁に変わらない業務
- 15. 単純作業で定期的に行われている業務
- 16. イレギュラーな事象がない業務
- 17. RPAの導入ならICにご相談ください
- 18. まとめ
RPAができることの具体例
RPA(Robotic Process Automation)は、パソコン上で人が行っている定型的な作業を自動化できるツールです。ルールに基づいた繰り返し業務を正確に処理するのが得意で、事務作業の効率化や人的ミスの削減に大きな効果を発揮します。ここでは、企業でよく導入される具体的な自動化業務の例を紹介します。
請求書作成業務
売上データや契約情報をもとに請求書を作成し、PDF化して取引先に送付する業務はRPAに任せることが可能です。従来は担当者が金額や日付を確認しながら手入力していたため、数十件~数百件の請求処理に数時間かかっていました。RPAを導入すれば、基幹システムからデータを抽出し、自動で請求書を生成してメール送信まで行えるため、処理時間は大幅に短縮。記載漏れや計算ミスといったヒューマンエラーも防止でき、経理部門の効率化に直結します。
口コミ・価格調査
競合商品の価格や顧客の口コミ情報を定期的にチェックする作業は、マーケティング担当にとって負担の大きい業務です。RPAはWebサイトにアクセスし、指定条件でデータを収集する「Webスクレイピング」を得意とするため、膨大な情報を短時間で収集できます。さらに、収集した情報をスプレッドシートに自動で整理することも可能です。これにより、市場変化をいち早く把握できるだけでなく、分析や戦略立案に素早く活用できるようになります。
発注リスト転記業務
仕入れ先から届いた発注データを、基幹システムやExcelに手作業で入力している企業は少なくありません。しかし人手による転記は時間がかかる上、数字の入力ミスやデータ抜けが発生するリスクがあります。RPAを導入すれば、発注リストを自動で読み込み、必要なフォーマットに合わせて転記処理が可能です。これにより、入力作業の時間を大幅に削減しつつ、精度の高いデータ処理が実現できます。特に物流や小売業での活用事例が多く見られます。
勤怠管理
従業員の出退勤データや休暇申請を集計し、勤怠システムに反映させる業務もRPAで自動化できます。これまでは人事部門がExcelや紙ベースのデータを一つひとつ確認して入力していましたが、RPAを使えば打刻データを収集し、残業時間や有給消化状況を即時に集計可能です。正確な勤怠管理が実現できるだけでなく、毎月の締め処理にかかっていた時間を大幅に短縮できるため、働き方改革の推進にもつながります。
顧客情報のシステム登録
営業活動で得た顧客情報をCRMや販売管理システムに登録する作業も、RPAが得意とする業務です。手作業では入力漏れや重複登録が発生しやすいですが、RPAであればExcelやフォームから自動的にデータを取り込み、指定されたフォーマットで登録できます。大量の顧客データを短時間で処理できるため、営業担当者は入力作業に時間を奪われず、顧客との関係構築や提案活動といった本来の業務に集中できます。
問い合わせ対応
メールやWebフォームから寄せられた問い合わせを自動で仕分け、内容に応じて適切な担当部署へ振り分けることもRPAで可能です。たとえば「請求関連」「製品仕様」「トラブル対応」といったカテゴリごとに自動分類し、簡単な問い合わせであれば定型文を自動返信することもできます。これにより、顧客への初動対応が早まり、担当者は複雑な案件に専念できるようになります。カスタマーサポート部門の負担を大幅に軽減できるのが魅力です。
入金確認業務
銀行口座の入出金明細を確認し、会計システムへ反映する作業は経理部門にとって毎日の必須業務ですが、細かい確認が必要で手間がかかります。RPAを導入すれば、オンラインバンキングからデータを自動取得し、入金情報を会計システムに照合・登録できます。これにより確認作業がスピーディかつ正確に行われ、未入金の検出や売掛金管理の精度も向上します。経理担当者は本来の分析業務や改善提案に時間を割けるようになります。
RPAができないこと

RPAはルールに従って動くソフトウェアであるため、万能ではありません。導入効果を最大化するためには「RPAが得意な業務」と「不得意な業務」を見極めることが重要です。ここでは代表的な「できないこと」を解説します。
自ら考えて判断すること
RPAはあくまで「決められた手順を繰り返す」ことが得意なツールであり、人間のように状況を見て判断したり、臨機応変に対応することはできません。たとえば「顧客からの問い合わせ内容を見て最適な提案をする」といった業務はAIや人間の判断が不可欠です。RPAは単独で意思決定を行うことはできないため、創造性や柔軟性を求められる仕事には適していません。
ルール変更が多く複雑な作業
RPAは設定されたルールに基づいて処理を行うため、業務ルールが頻繁に変わるとそのたびにシナリオを修正する必要があります。例えば請求書フォーマットや入力項目が月ごとに変わる業務では、メンテナンス工数が膨らみ、逆に効率が悪くなる可能性があります。また、処理手順が複雑すぎる業務では開発や維持管理のコストが高くなり、RPAの導入メリットが薄れてしまうケースもあります。
手書き文字や画像の解析
紙の書類に書かれた手書き文字を認識したり、画像や写真の内容を理解することは、RPA単体では対応できません。こうした作業にはOCR(光学文字認識)やAI画像解析などの技術と組み合わせる必要があります。たとえば手書きの申込書をデータ化する場合、OCRで文字を読み取り、その後の転記や集計をRPAに任せるといった使い分けが効果的です。RPAだけに頼るのではなく、他の技術と連携する視点が欠かせません。
RPAで自動化できる業務の考え方

RPAは万能なツールではなく、適した業務に導入することで初めて大きな効果を発揮します。ここでは「どのような業務がRPAに向いているか」を判断する際の3つの視点を解説します。
ルールが頻繁に変わらない業務
RPAは決められたルールに従って動作するため、業務手順や入力項目が安定している業務に適しています。例えば請求書処理や入金確認のように毎回同じ手順で処理する作業は、自動化することで高い効果を得られます。一方で、フォーマットや手順が頻繁に変わる業務は都度シナリオを修正しなければならず、運用負担が増えてしまいます。そのため「安定した業務かどうか」を見極めることが導入成功のポイントとなります。
単純作業で定期的に行われている業務
毎日・毎週・毎月など、定期的に繰り返される単純作業はRPAが最も得意とする領域です。売上データの集計や勤怠データの入力、顧客情報のシステム登録などは典型的な自動化対象です。人間が行うと時間がかかり、単調な作業で集中力が切れることもありますが、RPAであれば休むことなく正確に処理を続けられます。定期的に発生する作業を自動化することで、担当者はより付加価値の高い業務にシフトできます。
イレギュラーな事象がない業務
例外処理や個別対応が多い業務はRPAには不向きです。RPAは設定されたシナリオ通りにしか動けないため、想定外のエラーやイレギュラーな状況が発生すると処理が止まってしまう可能性があります。逆に、毎回同じ条件で処理できる業務であれば、自動化による効果は非常に大きくなります。例えば銀行の入出金確認や発注リストの転記といった、ルール通りに処理が進む業務はRPAの活躍に最適です。
RPAの導入ならICにご相談ください
RPAは正しく導入すれば大きな効果を発揮しますが、選定や設計を誤ると「思ったほど効率化できなかった」といった結果になりかねません。自社の業務に適した種類を見極め、スムーズに運用を定着させるには専門的な知識と経験が必要です。ICでは、業務分析からRPAツールの選定、導入後の改善まで一貫してサポートしています。小規模導入から全社展開まで、豊富な知見を活かした最適なプランをご提案しますので、ぜひご相談ください。
まとめ
RPAは請求書処理や入金確認、顧客情報登録といった定型業務を正確かつ効率的に実行できる強力なツールです。一方で、自ら判断を伴う業務やルール変更が多い業務には不向きであり、できることとできないことを理解したうえで導入することが重要です。
「ルールが安定している」「繰り返しの多い」「例外が少ない」業務から自動化を始めれば、効率化やミス削減、働き方改革につながります。RPAを自社にどう活かすべきか迷っている方は、専門知識を持つICに相談することで、確実に成果を得られる導入を実現できるでしょう。
前の記事

Google Workspaceの活用法・事例や使い方のポイントを解説
次の記事

Google WorkspaceとMicrosoft 365を徹底比較!機能・料金・選び方を解説