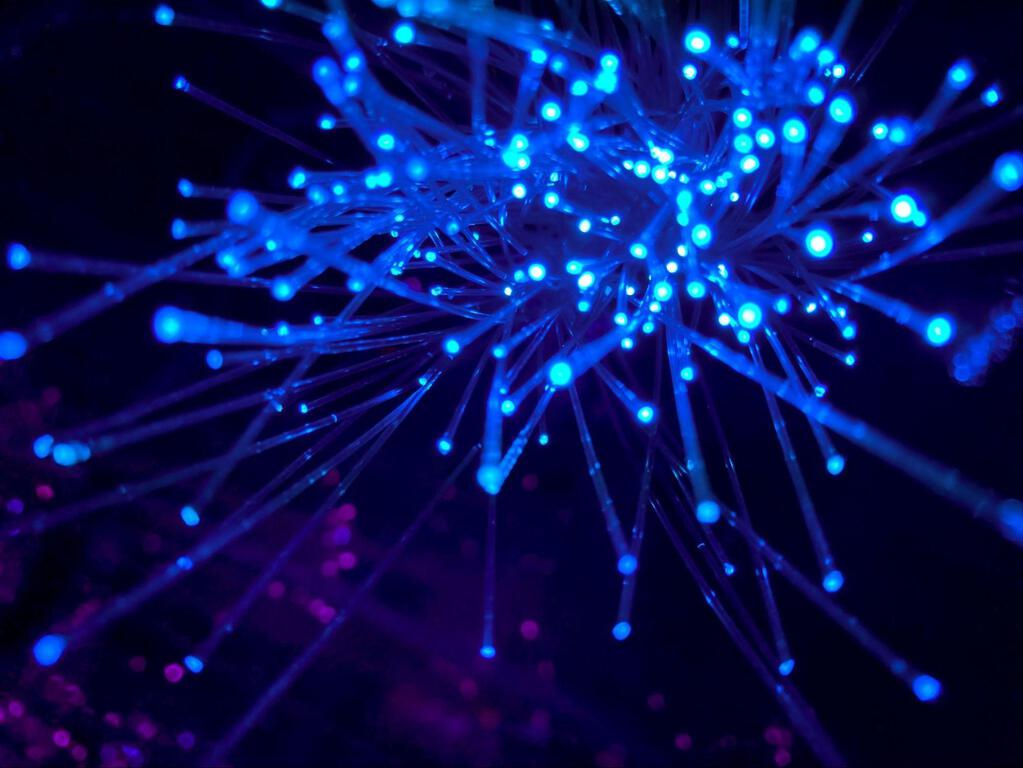Outsystemsと他ローコードツールの違いは?事例・失敗例から見る導入のポイント
ローコード開発が一般化する中で、「Outsystems(アウトシステムズ)」は特に大規模・複雑な業務システムに対応できるプラットフォームとして注目されています。
多くの企業がローコード開発を検討する際、「どのツールを選べばいいのか」「Outsystemsは他と何が違うのか」といった疑問を抱えています。
本記事では、Outsystemsが他のローコードツールとどう異なるのかを徹底解説。活用事例や導入時によくある失敗例、導入に適した企業の特徴まで、導入判断の参考になる情報を網羅しています。
Outsystemsの特長を正しく理解し、自社に最適な開発環境を選びたい方はぜひご覧ください。
目次
- 1. Outsystemsはどんなローコード開発プラットフォーム?
- 2. Outsystemsと他のローコード開発ツールの違い
- 3. 大規模なシステム開発に適している
- 4. ノーコード・ローコード開発の範囲を超えたカスタマイズが可能
- 5. UI/UXやレスポンス管理の柔軟さが高い
- 6. 導入前〜運用後までの一貫した支援体制が整っている
- 7. Outsystemsの活用事例
- 8. Outsystems導入における失敗事例とその原因
- 9. 内製を急ぎすぎて社内リソースが不足している
- 10. 既存システムとの連携が複雑すぎて頓挫してしまう
- 11. Outsystemsを選ぶべき企業の特徴
- 12. 開発リソースが限られている企業
- 13. DX推進やレガシーシステムのモダナイズを課題としている企業
- 14. セキュリティ・運用基盤を重視する企業
- 15. 複雑な業務ロジックや外部システム連携が必要な企業
- 16. 将来的なアプリ拡張やユーザー数の増加を見込んでいる企業
- 17. Outsystemsでのアプリ開発ならICへ
- 18. まとめ
Outsystemsはどんなローコード開発プラットフォーム?
Outsystems(アウトシステムズ)は、ポルトガル発のローコード開発プラットフォームで、ビジュアル操作によってWeb・モバイルアプリを効率的に開発できるツールです。従来のコーディング開発と比較して圧倒的なスピードを誇り、エンタープライズレベルの複雑な要件にも対応できる点が大きな特徴です。
一般的なローコードツールの多くが「簡易な業務アプリ」や「画面開発支援」に特化している一方、Outsystemsは、要件定義から開発・テスト・リリース・運用・改善まで、アプリケーションライフサイクル全体をカバーしています。さらに、AIによるロジック補完や、堅牢なセキュリティ機能、テンプレートの活用による高品質なUI/UX設計にも対応しており、大手企業を中心に導入が進んでいます。
Outsystemsについては、以下の記事でも詳しく紹介しています。
Outsystemsと他のローコード開発ツールの違い
ローコード開発ツールは数多く存在しますが、その中でもOutsystemsは「大規模開発」や「拡張性の高い業務システム構築」に強みを持っています。以下では、Outsystemsが他のローコードツールと異なる点を、主な観点ごとに整理してご紹介します。
大規模なシステム開発に適している
Outsystemsは、複数部署や外部パートナーを巻き込んだ大規模な開発体制にも対応できる設計思想を持っています。プロジェクトの進行に必要な環境(開発・テスト・本番)を一元管理できるうえ、依存関係の自動検知や、バージョン管理、パフォーマンス監視機能などが標準で備わっています。
そのため、開発者が10名以上にわたるような体制でも、品質を保ったままスピーディに開発を進めることが可能です。中小規模向けのツールでは対応が難しい、複雑で長期的な開発にも十分耐えうる基盤が整っています。
ノーコード・ローコード開発の範囲を超えたカスタマイズが可能
多くのローコードツールでは、テンプレートや機能ブロックに制限があり、「そこから先の拡張」が難しくなるケースがあります。しかしOutsystemsでは、JavaScriptやC#などによるカスタムコードの埋め込みや、API・外部システムとの連携も柔軟に対応できます。
つまり、ローコードで可能な範囲はビジュアル操作で迅速に構築しつつ、必要に応じてコードによる柔軟な開発も可能な、いわば“ハイブリッド”な開発スタイルを実現できます。
UI/UXやレスポンス管理の柔軟さが高い
Outsystemsには、デザイン性の高いUIパーツや画面テンプレートが豊富に用意されており、モバイル対応も含めて洗練されたアプリケーションを短時間で構築できます。また、レスポンシブデザインやデバイスごとの最適化機能も自動で適用されるため、フロントエンドの開発負荷を大きく軽減できます。
さらに、Webアプリ・モバイルアプリを同一の操作で構築できる点も、開発チーム全体の学習コストと運用負担を削減する大きなメリットです。
導入前〜運用後までの一貫した支援体制が整っている
Outsystemsは、単なる開発ツールではなく「アプリケーションライフサイクル管理(ALM)」の考え方に基づいた製品です。開発開始前の設計支援や、開発プロジェクトにおける進行管理、テスト・検証、そして本番環境への移行やパフォーマンス監視までをカバーします。
この一貫性こそが、Outsystemsが他のローコード製品と一線を画す理由のひとつです。社内開発だけでなく、SIerやパートナーとの共同開発にも強く、長期的な運用視点で導入を検討する企業に特に向いています。
Outsystemsの活用事例
ここでは、弊社がOutsystemsを活用しシステムのリプレイスを行った事例について紹介します。
既存の販売管理システムが老朽化・保守切れを迎える中、Outsystemsを活用して、代理店が利用する販売・請求業務システムのリプレイスを実施した事例です。
新システムでは、従来の仕様を踏襲しながらも、請求書の発行方式など細かな改善要望に対応。Outsystemsのテンプレートやビジュアル設計機能を活用することで、使いやすく、かつ高品質なUIを短期間で構築しました。
また、移行時には大量データを扱うバッチ処理の設計から着手し、エラーを抑える仕組みを徹底。最終的には、全国の利用者への展開を段階的に進めながら、大きなトラブルもなく移行を完了しました。
現在も本システムの保守運用を継続しており、評価を受けたことで別業務システムへのOutsystems展開も進行中です。
詳しい事例は、以下の記事でご確認いただけます。
Outsystems導入における失敗事例とその原因

Outsystemsは非常に高機能なローコード開発プラットフォームですが、導入や運用において十分な準備ができていないと、思わぬ課題に直面することもあります。ここでは、実際によく見られる失敗パターンとその原因について紹介します。
内製を急ぎすぎて社内リソースが不足している
Outsystemsは操作性が高いため、「自社だけで内製化できるだろう」と過信して導入を進めた結果、開発体制が追いつかずに頓挫するケースがあります。
特に初期導入時には、プラットフォームの特性や設計思想に習熟するまで一定の時間がかかります。設計から開発、テスト、リリースまでの一連のプロセスを社内だけで賄おうとすると、担当者の負荷が高まり、プロジェクトが遅延する可能性があります。
こうしたケースでは、最初は専門パートナーと連携し、段階的に内製化を進めることが現実的です。
既存システムとの連携が複雑すぎて頓挫してしまう
Outsystemsは外部システムとの連携に強い反面、既存の基幹システムが古く、仕様が不明確な場合やドキュメントが残っていない場合、連携の設計に大きな手間がかかることがあります。
結果として、想定していた開発スケジュールに間に合わなかったり、連携部分の実装にバグや不整合が生じてしまうケースも少なくありません。
導入前には、既存システムとの接続可否や仕様確認を十分に行い、必要に応じて段階的な切り替えや部分リプレイスも視野に入れることが重要です。
Outsystemsを選ぶべき企業の特徴
Outsystemsは汎用的なローコードツールとは異なり、開発規模や業務要件によって向き不向きがあります。以下のような課題や要望を持つ企業にとって、Outsystemsは非常に有効な選択肢となります。
開発リソースが限られている企業
社内に十分な開発人材を確保できていない、あるいはIT部門が少数で多くの案件を抱えている企業にとって、Outsystemsは強力な味方になります。視覚的な操作やテンプレートを活用することで、少人数でも高機能な業務アプリの構築が可能となり、スピードと効率を両立できます。
DX推進やレガシーシステムのモダナイズを課題としている企業
古い基幹システムの更新が進まず、DXのボトルネックになっている企業にとって、Outsystemsはその課題を解決する手段になり得ます。部分的な機能置き換えや段階的なシステム統合も柔軟に対応できるため、無理のないペースでモダナイズを進められます。
セキュリティ・運用基盤を重視する企業
Outsystemsは、アクセス制御・通信の暗号化・ログ管理など、企業ITに求められるセキュリティ機能を標準で備えています。また、複数の環境(開発・テスト・本番)を統合的に管理できる運用体制も構築しやすく、ガバナンスや監査対応が必要な企業に適しています。
複雑な業務ロジックや外部システム連携が必要な企業
テンプレート主体のノーコードツールでは対応しきれないような複雑な処理や、複数システムとのデータ連携が求められる企業には、柔軟なカスタマイズが可能なOutsystemsが最適です。REST/SOAP/SAPなどさまざまなインターフェースに対応しており、業務全体の最適化を支援します。
将来的なアプリ拡張やユーザー数の増加を見込んでいる企業
将来的にシステムの拡張やユーザー数の増加が見込まれる場合にも、Outsystemsは有利です。アプリの再構築や移行を必要とせずに拡張できる設計になっており、ビジネスの成長に合わせた柔軟な対応が可能です。
Outsystemsでのアプリ開発ならICへ

引用:システム開発のIC
Outsystemsの導入・活用を成功させるには、ツールを使いこなすだけでなく、業務要件の整理や移行計画、運用フェーズまで見据えた総合的な設計が欠かせません。
ICは、Outsystemsを活用した業務システムの開発・リプレイスにおいて豊富な実績を持つパートナーです。実際に、大手建材メーカー様の販売管理システムをOutsystemsで全面再構築したプロジェクトでは、複雑な業務要件と大量データの処理を高品質・短納期で実現。移行後もエラーの少ないシステムとして高く評価され、現在も保守運用を継続しています。
ICでは、要件定義から開発、テスト、移行、保守に至るまで一貫して支援。Outsystemsの特性を最大限に活かしながら、企業の現場に寄り添ったアプリ開発を実現します。
「内製化を進めたい」「レガシーシステムを段階的に更新したい」「拡張性の高い業務アプリを短期間で構築したい」といった課題をお持ちの企業様は、ぜひ一度ご相談ください。貴社のニーズに合わせた最適な開発体制をご提案いたします。
まとめ
Outsystemsは、ローコード開発の領域を超えた柔軟性と拡張性を持ち、企業のアプリ開発・DX推進を強力に後押しするプラットフォームです。
一般的なローコードツールと比較して、大規模開発への対応力や、業務に即した高度なカスタマイズ、堅牢な運用基盤を備えている点が大きな強みです。
一方で、導入にあたっては社内体制や既存システムとの連携設計に注意が必要です。初期段階から実務に通じたパートナーと取り組むことで、失敗リスクを最小限に抑え、スムーズな立ち上げと運用が可能になります。
Outsystemsの特長や他ツールとの違いを理解し、自社の状況に合った導入戦略を立てることで、長期的に価値ある開発基盤を構築できるでしょう。
Outsystemsの導入をご検討の際は、ぜひICにご相談ください。豊富な実績と現場目線のサポートで、貴社のシステム変革を支援いたします。
前の記事

Outsystemsとは?何ができる?特徴やメリット、事例を紹介
次の記事

Google Workspaceとは?できることや導入のメリットを解説