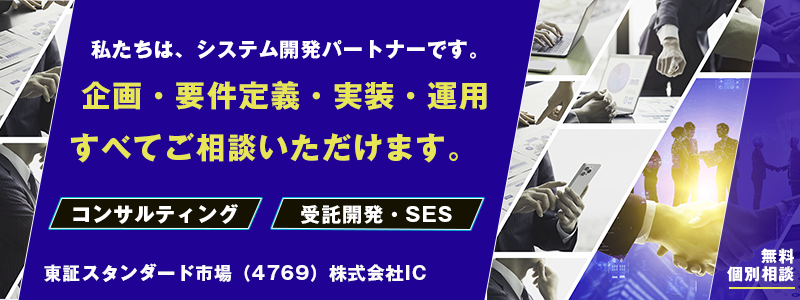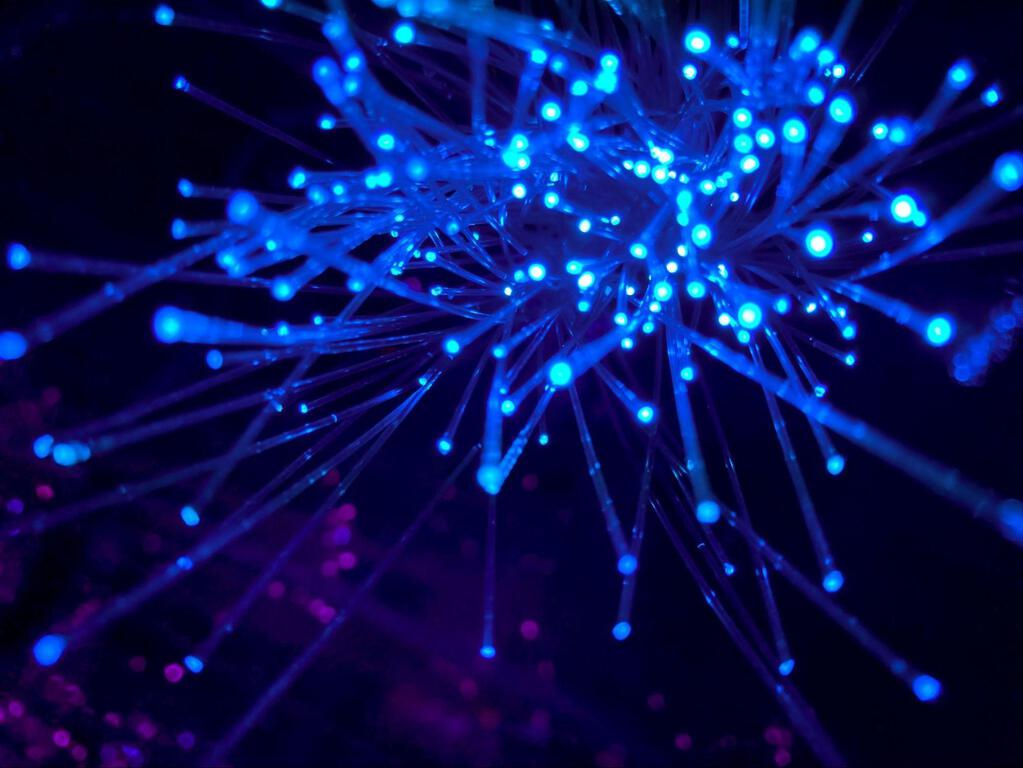システムのライフサイクルとは?フェーズとモデルをわかりやすく解説
システム開発やIT運用に関わる中で、「全体像が見えにくい」「開発はうまくいったが運用でつまずいた」といった課題に直面した経験はありませんか?そうした問題を防ぐために重要となるのが、「システムライフサイクル」の理解です。
本記事では、システムライフサイクルの概要から各フェーズの内容、代表的な開発モデル、管理上のポイント、そして現場でよくある課題までを分かりやすく解説します。システム企画や運用に関わる担当者の方はぜひ参考にしてください。
目次
- 1. システムライフサイクルとは
- 2. システムライフサイクルの主なフェーズ
- 3. 企画・要求定義
- 4. 要件定義
- 5. 設計
- 6. 開発・実装
- 7. テスト
- 8. 展開・リリース
- 9. 運用・保守
- 10. 改善
- 11. システムライフサイクルのモデル
- 12. ウォーターフォールモデル
- 13. アジャイルモデル
- 14. 反復型モデル
- 15. スパイラル(漸進)型モデル
- 16. V字型モデル
- 17. プロトタイプモデル
- 18. ハイブリッド型モデル
- 19. システムライフサイクルで意識すべきこと
- 20. 適切なライフサイクルモデルを選択する
- 21. ステークホルダーとの合意形成を意識する
- 22. 定期的なメンテナンスと改善を前提にする
- 23. ライフサイクル管理でよくある課題
- 24. フェーズごとの担当分担が曖昧
- 25. 開発から運用への引き継ぎ不足
- 26. コストやリソース配分の見積もり不足
- 27. ICのITソリューションならシステムの企画から運用まで支援
- 28. まとめ
システムライフサイクルとは
システムライフサイクルとは、ITシステムが企画・設計されてから開発、運用、そして廃棄に至るまでの一連の工程を指す概念です。英語では「System Development Life Cycle(SDLC)」とも呼ばれ、システムを開発・管理していく上での基本的な枠組みとして、多くの企業や組織で活用されています。
このライフサイクルを理解することは、システム開発や運用のプロジェクトを効率よく、かつ確実に進行させる上で欠かせません。各フェーズで何を行うべきかを明確にすることで、後戻りのない設計・開発が可能となり、トラブルや手戻り、コストの無駄を防ぐことにもつながります。
また、ライフサイクル全体を通じた視点を持つことで、導入後の運用保守や将来的な改修まで見据えた長期的なIT戦略の構築が可能になります。情報システム部門やIT担当者がシステムの全体像を把握し、適切な管理と判断ができるようになることが、組織全体の生産性や競争力向上にも直結するのです。
システムライフサイクルの主なフェーズ
システムライフサイクルは、システムが誕生してから廃棄・更新されるまでのプロセスを段階的に表したもので、一般的には「企画」から「改善」までのフェーズに分かれています。それぞれのフェーズで適切なプロセスを踏むことで、システムの品質と業務への貢献度を最大化することが可能です。
企画・要求定義
システムライフサイクルの最初のステップは、ビジネス上の課題やニーズを整理し、システム導入の目的を明確にすることです。この段階では「なぜこのシステムが必要なのか」「何を実現したいのか」といった大枠の方向性を決定します。業務部門や経営層と連携し、要望や制約条件をヒアリングすることが重要です。
要件定義
企画フェーズで明確になった目的をもとに、より具体的な「機能要件」や「非機能要件(セキュリティ・可用性・性能など)」を定義します。この段階では、システムが何をするのか、どのように動作するのかを仕様として言語化し、開発チームとの認識を一致させることが求められます。要件定義の精度は、後続フェーズの品質に大きく影響します。
設計
要件定義でまとめた仕様に基づき、システムの構造や画面設計、データベースの構成などを具体的に設計していくフェーズです。基本設計と詳細設計に分かれ、利用者の使いやすさや保守性、セキュリティ面を考慮しながら、実装可能な形に落とし込んでいきます。
開発・実装
設計書をもとに、実際のシステムを構築する工程です。プログラミングやインフラ構築、外部サービスとの連携などがこの段階で進行します。品質を保つためには、進捗管理やコードレビュー、テストの前倒し実施などが求められます。小規模な開発でも、フェーズごとの進行管理は欠かせません。
テスト
開発されたシステムが設計通りに動作するかどうかを確認するフェーズです。単体テスト、結合テスト、システムテスト、ユーザーテストなど複数段階でのテストを通じて、不具合の検出と修正を行います。このフェーズを徹底することで、リリース後のトラブルを未然に防ぎます。
展開・リリース
テストが完了したら、システムを本番環境に反映し、実際の業務で使用できる状態に移行します。必要に応じてデータ移行やユーザー教育、導入支援を行い、スムーズな立ち上げをサポートします。この段階では、業務影響を最小限に抑えるための周到な準備と計画が不可欠です。
運用・保守
システムが稼働し始めた後も、業務に支障が出ないように日常的な運用管理と障害対応、定期的なメンテナンスが必要です。また、業務や環境の変化に応じて、機能追加や改善も行われます。このフェーズが長期にわたるため、運用性や保守性を設計段階から意識しておくことが重要です。
改善
運用を続ける中で、システムに求められる要件や環境は変化していきます。こうした変化に対応するために行うのが「改善」です。必要に応じて再度、要件定義や設計、テストを実施し、システムの性能や利便性を高めます。
また、老朽化や新しい技術の登場により、より自社のニーズに合ったシステムへ移行するケースもあります。こうした改善や再構築を経て、新たなシステムライフサイクルが再び始まります。
システムライフサイクルのモデル

システム開発においては、ライフサイクルの各フェーズをどのように進行・管理するかがプロジェクトの成否を左右します。その進め方の指針となるのが「開発モデル(開発手法)」です。目的や規模、要件の明確さなどに応じて適切なモデルを選択することで、品質や納期、コストの最適化が図れます。ここでは代表的な7つの開発モデルをご紹介します。
ウォーターフォールモデル
ウォーターフォールモデルは、工程を上から下へ順番に進める開発手法で、最も基本的かつ古典的なモデルです。企画・要件定義から設計、開発、テスト、リリースまでを一方向に流れるように進行します。各工程の成果物が次の工程の前提となるため、要件が明確な大規模開発や公共系プロジェクトに適しています。ただし、一度戻るのが難しいため、途中の仕様変更には向いていません。
アジャイルモデル
アジャイルモデルは、小さな単位で開発とリリースを繰り返す柔軟な手法です。開発初期から実際のユーザーに触れてもらい、フィードバックを得ながら進化させていくスタイルで、変化の激しい業務や短期サイクルで改善が求められるシステムに最適です。ウォーターフォールと比べてスピード感がありますが、関係者との密なコミュニケーションと継続的な調整が不可欠です。
反復型モデル
反復型モデルは、システム全体を一度に作り上げるのではなく、機能ごとに段階的に設計・開発・テストを繰り返す手法です。部分的にリリースしながら全体を仕上げていくため、完成までの過程でユーザーのニーズを確認しつつ調整が可能です。アジャイルに近い考え方ですが、より段階的かつ構造的に進められるのが特徴です。
スパイラル(漸進)型モデル
スパイラル型モデルは、リスク分析を取り入れた漸進的な開発アプローチです。複数の反復開発サイクルを円(スパイラル)状に展開し、各サイクルで「計画 → リスク分析 → 開発 → 評価」を実施します。特に不確定要素の多いプロジェクトや、試験的な開発を行いたい場面で有効です。リスク対策を重視しながら段階的に完成度を高めていく点が特徴です。
V字型モデル
V字型モデルは、ウォーターフォールモデルの構造に「テスト工程」を強く組み込んだモデルです。開発プロセスの左側が要件定義〜設計、右側がそれぞれの工程に対応したテストとなっており、V字の形を描くように進行します。品質保証を重視する現場で採用されることが多く、要件定義や設計段階でテスト計画を立てることで、ミスの早期発見につながります。
プロトタイプモデル
プロトタイプモデルは、まず試作品(プロトタイプ)を作成し、ユーザーの反応やフィードバックをもとに仕様を固めていく開発手法です。要件が曖昧な場合や、完成イメージを事前に確認したい場合に効果的で、ユーザーとのコミュニケーションを重視したアプローチです。ただし、試作品がそのまま本番に流用されると品質リスクを伴うため、慎重な設計が求められます。
ハイブリッド型モデル
ハイブリッド型モデルは、複数の開発モデルの長所を組み合わせた柔軟なアプローチです。たとえば、基幹部分はウォーターフォールで堅実に進め、ユーザーインターフェース部分はアジャイルで開発するといった使い分けが可能です。プロジェクトの特性や体制、開発スピードに応じて適切な手法を柔軟に取り入れられるのが大きなメリットです。
システムライフサイクルで意識すべきこと
システムライフサイクルを効果的に管理・活用するためには、単に工程を順にこなすだけではなく、プロジェクト全体を見通した判断と運用が求められます。ここでは、ライフサイクル管理において特に重要となる3つの視点を紹介します。
適切なライフサイクルモデルを選択する
システムの目的や規模、要件の明確さ、開発期間、組織体制などに応じて、どの開発モデルを採用するかは非常に重要な判断です。たとえば、要件が固まっているシステムではウォーターフォールモデルが適していますが、仕様の変化が予想されるシステムではアジャイルや反復型モデルの方が柔軟に対応できます。
一律に同じモデルを使うのではなく、案件の特性を見極めて最適なアプローチを選ぶことで、品質・スケジュール・コストのバランスを取りやすくなります。
ステークホルダーとの合意形成を意識する
ライフサイクルの各フェーズでは、システム部門だけでなく、利用部門や経営層など、複数の関係者(ステークホルダー)との調整が必要になります。要件定義や設計の段階で関係者の合意が不十分だと、後工程での手戻りやトラブルにつながる可能性が高まります。
そのため、プロジェクトの早い段階からステークホルダーとの情報共有を密に行い、期待値や役割を明確にしたうえで、段階的な合意形成を図ることが重要です。
定期的なメンテナンスと改善を前提にする
システムはリリースして終わりではなく、運用フェーズに入ってからが本番とも言えます。業務の変化やセキュリティリスクの増加に対応するためには、定期的なメンテナンスや改善が不可欠です。
初期設計の段階から、将来的な拡張や変更を見越した柔軟な構成にしておくことや、保守運用に関するルールや手順を整備しておくことで、長期的な運用コストやトラブルの発生を抑えることができます。システムの「持続可能性」を考慮した設計・運用が求められます。
ライフサイクル管理でよくある課題
システムライフサイクルを円滑に進めるには、計画・実行・管理の各段階で的確な判断と調整が求められます。しかし、現場ではさまざまな課題に直面することが多く、プロジェクトの遅延や品質低下につながることもあります。ここでは、システムライフサイクルにおいてありがちな代表的な課題を3つ紹介します。
フェーズごとの担当分担が曖昧
システムライフサイクルには複数のフェーズが存在し、それぞれに異なるスキルや知識が求められます。しかし、社内で明確に担当が決まっていない場合、責任の所在が不明確となり、作業の抜け漏れや非効率な進行が発生しがちです。
たとえば、設計と開発の間で仕様の受け渡しが不十分だったり、保守担当者が要件を把握していないといった事例がよくあります。各フェーズごとに担当者と役割を明確化し、ドキュメントや情報を正しく引き継ぐ体制づくりが重要です。
開発から運用への引き継ぎ不足
システムの本番稼働後、「運用部門が設計思想を理解していない」「ドキュメントが不足している」といった理由でトラブルが発生することは少なくありません。開発フェーズが完了した段階で運用担当者への引き継ぎが不十分だと、障害対応や設定変更に支障をきたします。
スムーズな引き継ぎを行うためには、運用マニュアルの整備やトレーニングの実施、試験的な運用期間を設けるなどの工夫が必要です。開発側と運用側の協力体制を事前に築いておくことも、重要なポイントです。
コストやリソース配分の見積もり不足
ライフサイクル全体を通じた予算や人員の見積もりが甘いと、途中でコストが膨らんだり、リソースが不足してスケジュールが遅延するリスクが高まります。特に、運用・保守フェーズのコストや労力を軽視しがちで、リリース後に思わぬ負担が発生するケースも見受けられます。
ライフサイクルの各工程に必要な工数・人員・予算をできるだけ精度高く見積もり、変化に応じて柔軟に調整できる体制を整えておくことが、プロジェクト成功の鍵となります。
ICのITソリューションならシステムの企画から運用まで支援

出典:システム開発のIC
システムライフサイクルを正しく管理し、効果的な開発・運用を実現するためには、各フェーズでの専門的な知識や豊富な経験が不可欠です。特に企画段階での要件整理や、運用フェーズへのスムーズな移行は、システムの長期的な成功を左右する重要なポイントとなります。
ICでは、システムの企画・要件定義から設計・開発・運用保守に至るまで、ライフサイクル全体を一貫して支援するITソリューションを提供しています。企業の業種や業務内容、ITリソースに応じて、最適な開発モデルの選定から体制構築、実行支援までをトータルでサポート。プロジェクトの初期段階から関わることで、手戻りの少ない設計や、運用を見据えた仕様策定が可能になります。
また、導入後も継続的な改善提案や運用効率化のサポートを行い、IT部門の負担軽減と業務全体の最適化を支援します。システムの全体像を見渡しながら、確実かつ柔軟な体制で企業のIT戦略を支えるパートナーとして、ぜひICをご活用ください。
まとめ
システムライフサイクルは、単なる開発プロセスではなく、企画から運用・改善までを見据えた一連のサイクルです。この全体像を正しく理解し、各フェーズで何を行うべきかを把握することで、無駄のない開発や効率的な運用が実現できます。
ライフサイクルの管理には、適切なモデル選定や関係者との合意形成、長期的な視点でのメンテナンス計画が欠かせません。一方で、現場では分担の曖昧さや引き継ぎの不足、コスト見積もりの甘さといった課題に直面することも少なくありません。
こうした課題を乗り越え、システムを確実に成功へ導くためには、外部の専門的な支援を活用するのも有効な選択肢です。ICのITソリューションは、システムのライフサイクルを包括的に支援し、企業のIT基盤の強化と業務改善を力強く後押しします。
前の記事

Google Workspace導入ガイド|手順・注意点・導入支援サービスまで解説
次の記事

Windows Serverとは?特長やメリット、導入方法まで解説