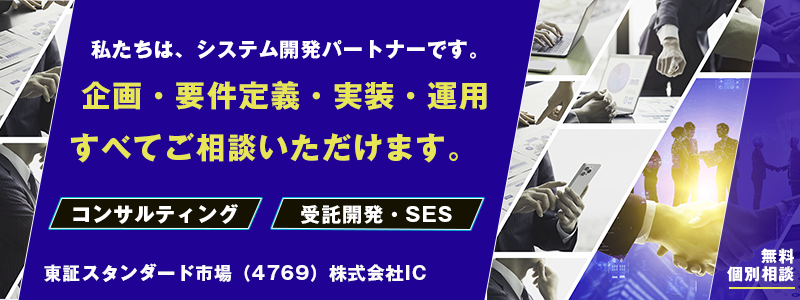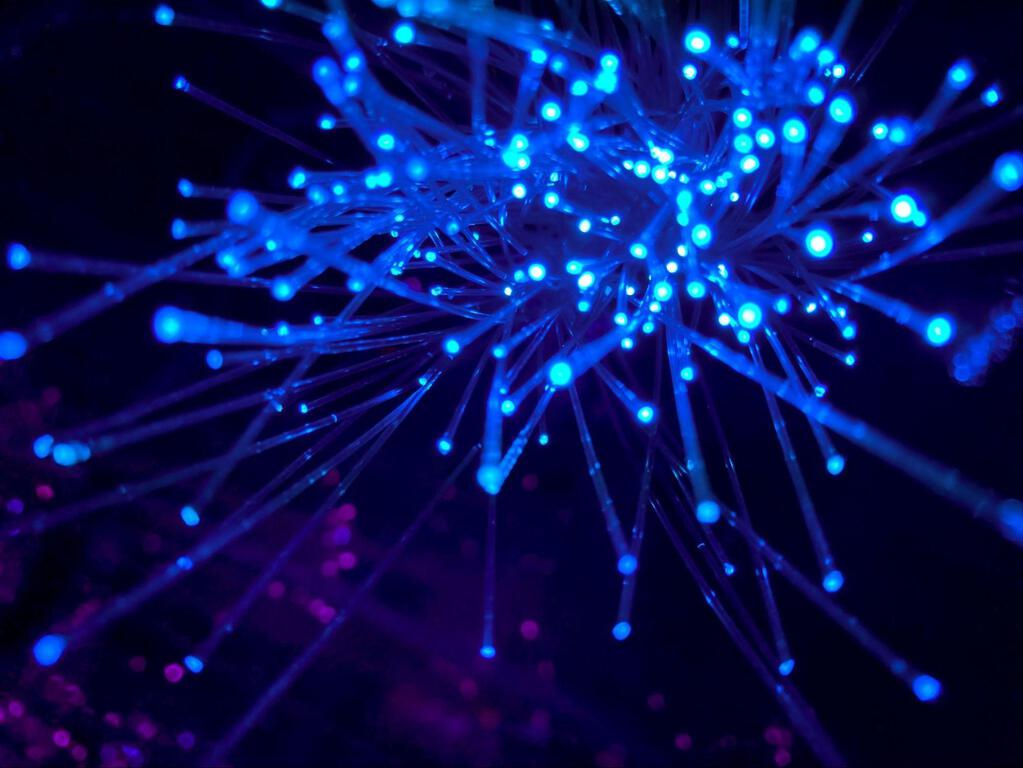RPAとAIの違いとは?組み合わせによる業務効率化と活用事例を解説
近年、多くの企業で業務効率化や人材不足への対応策として注目を集めているのがRPAとAIです。RPA(Robotic Process Automation)は、定型的で繰り返し発生する事務作業をソフトウェアロボットが代行する仕組みで、短期間での効果が期待できる技術です。
一方、AI(Artificial Intelligence/人工知能)は大量のデータを学習してパターンを見出し、予測や判断を行うことに強みを持ち、複雑で非定型な業務の効率化に役立ちます。
両者はそれぞれ特徴が異なりますが、組み合わせることで幅広い業務を自動化できる点が大きな魅力です。
本記事では、RPAとAIの基本的な違いや活用方法、具体的な事例、導入時に押さえておくべき課題について解説し、企業が自社に合った活用方法を見つけるためのヒントをお伝えします。
目次
- 1. RPAとは
- 2. RPAの種類
- 3. RPAの得意分野
- 4. AIとは
- 5. AIの得意分野
- 6. AIの種類
- 7. RPAとAIの違い
- 8. 得意分野の違い
- 9. 導入コスト・運用体制の違い
- 10. 活用シーンの違い
- 11. RPAとAIを組み合わせるメリット
- 12. RPA×AI-OCRで紙帳票をデジタル化
- 13. RPA×対話型AIで顧客対応を効率化
- 14. RPA×AIでマーケティングや需要予測を最適化
- 15. RPA×AIで製造ラインや人員配置を改善
- 16. RPA×AIの活用事例
- 17. 自治体における申請処理の効率化
- 18. 銀行での口座開設・審査業務の自動化
- 19. 人材サービス業におけるマッチング精度向上
- 20. 流通・小売での需要予測と在庫管理
- 21. RPA・AI導入時の課題と注意点
- 22. 導入コストとROIの見極め
- 23. 現場スタッフへの定着支援
- 24. セキュリティ・ガバナンスの確保
- 25. ICはRPA×AI活用をサポートします
- 26. まとめ
RPAとは
RPA(Robotic Process Automation)は、人がコンピューター上で行っている定型的な作業をソフトウェアロボットに代行させる仕組みです。たとえば、Excelでのデータ集計、基幹システムへの入力、メール送受信、Webサイトからの情報取得など、日常的に繰り返される業務を自動化できます。
従来、システムの自動化には大規模な開発や改修が必要でしたが、RPAは既存のシステムをそのまま活かし、画面操作を模倣して動作するため、導入までのハードルが低い点が特長です。人手による作業時間の削減や、ヒューマンエラー防止といった効果が期待でき、多くの企業で業務効率化の手段として導入が進んでいます。
RPAの種類
RPAは導入の形態や利用シーンに応じて、主に次の3種類に分類されます。
アテンド型RPA
利用者のパソコン上で動作し、作業を補助する形で動くタイプです。人が確認や判断を行いながら、一部の単純作業を自動化できます。
アンアテンド型RPA
サーバー上で動作し、人の操作を必要とせずに自律的に処理を行います。夜間や休日に大量のバッチ処理を行うなど、完全自動化に適しています。
ハイブリッド型RPA
アテンド型とアンアテンド型を組み合わせたタイプで、業務内容に応じて柔軟に使い分けられます。ユーザーの操作支援と完全自動化の双方を実現できます。
RPAの得意分野
RPAが最も力を発揮するのは「ルールが明確で繰り返し行われる作業」です。たとえば以下のような業務が代表的です。
会計や人事システムへの定型入力
複数システム間のデータ転記
定期的なレポート作成や送信
Webからの情報収集・更新作業
こうした業務は人手で行うと時間がかかり、入力ミスなどのリスクも伴います。RPAを導入すれば、作業スピードの向上と品質の安定化を両立でき、従業員はより付加価値の高い業務に時間を割けるようになります。
AIとは
AI(Artificial Intelligence/人工知能)は、人間の知的活動をコンピューターで模倣し、学習や判断を行う技術を指します。特に近年は「機械学習」や「ディープラーニング」といった技術の進化により、AIは急速に実用化が進んでいます。
AIは人間の経験や直感に頼っていた領域を数値化し、膨大なデータをもとに高精度な予測や判断を行えることが大きな特長です。
たとえば、過去の販売実績から需要を予測する、画像を解析して不良品を検出する、顧客の質問に自然な文章で回答するなど、人間の知能を補完する役割を担います。
RPAが「定められた手順を繰り返すこと」に優れるのに対し、AIは「学習しながら柔軟に対応すること」に強みがあり、両者の違いを理解することは業務への適用を考えるうえで重要です。
AIの得意分野
AIが最も力を発揮するのは、ルール化が難しく、大量のデータを処理して分析や判断が必要な業務です。たとえば、製造業では画像認識を活用して生産ライン上の不良品を検出することができます。
金融業では、取引データをもとに不正検知を行い、リスクを未然に防ぐことが可能です。また、自然言語処理を使ったチャットボットや音声認識システムは、顧客対応の効率化に貢献しています。
さらに小売・流通業界では、過去の購買データをAIが学習し、需要を予測することで在庫管理や販売戦略を最適化できます。
このようにAIは、膨大なデータを素早く分析し、人間が見落としがちなパターンを発見することに優れているため、幅広い業種で導入が進んでいます。
AIの種類
AIには複数の技術領域が存在し、それぞれが異なる目的で利用されています。代表的なのが「機械学習」で、過去のデータから傾向を学習し、将来のデータに基づいて予測や分類を行います。
さらに進化した「ディープラーニング」は、多層のニューラルネットワークを活用して特徴を自動抽出し、画像認識や音声認識といった高度な処理を実現します。
また「自然言語処理(NLP)」は、人間の言葉を理解・生成する技術で、チャットボットや翻訳サービス、文章要約などに活用されています。
さらに「強化学習」は、試行錯誤を繰り返しながら最適な行動を学習する仕組みで、自動運転やロボット制御の分野で成果を上げています。
このようにAIは用途ごとに多様なアプローチがあり、目的に応じて最適な技術を選ぶことが重要です。
RPAとAIの違い

RPAとAIはいずれも業務効率化を実現するための技術ですが、得意とする領域や仕組みは大きく異なります。RPAは人間が行う定型的な操作を忠実に再現することに強みを持ち、AIは大量のデータをもとに学習し、判断や予測を行える点が特徴です。両者を混同すると導入効果を正しく評価できないため、それぞれの違いを理解しておくことが重要です。ここでは、得意分野・導入コストや運用体制・活用シーンという3つの観点から整理します。
得意分野の違い
RPAの得意分野は、ルールが明確で手順が一定している業務です。たとえば会計システムへの入力や、複数システム間のデータ転記、日次・月次で繰り返される定期的なレポート作成などがあります。
これらは人間が行うと時間がかかり、入力ミスのリスクも避けられませんが、RPAであれば高速かつ正確に実行できるため、生産性と品質を同時に向上させることができます。
一方、AIは大量のデータを分析し、そこから傾向や異常を見つけ出すことに強みがあります。
需要予測や顧客データの分析、不良品検知、自然言語処理を活用した問い合わせ対応など、人間が直感や経験で行っていた判断をサポートし、より高度な意思決定を可能にします。
導入コスト・運用体制の違い
RPAは比較的短期間かつ低コストで導入できるのが特徴です。ソフトウェアを導入すればすぐに運用を開始でき、専門的なプログラミング知識がなくても、業務部門の担当者が中心となって管理することも可能です。
小規模な業務からスモールスタートできるため、ROI(投資対効果)を実感しやすい点も大きな魅力です。これに対し、AIは学習に必要なデータの収集や、アルゴリズムの構築、モデルのチューニングなど高度な作業が伴います。
そのため導入コストは比較的高く、また導入後も継続的な運用体制の構築が求められるため、IT部門や専門ベンダーとの連携が欠かせません。この点で、RPAとAIは初期導入の負担や運用体制に大きな違いがあります。
活用シーンの違い
RPAの活用シーンは、毎日発生する定型作業や繰り返し処理が中心です。たとえば、請求書の発行や入金消込、基幹システムへの入力業務など、人間がルール通りに処理していた作業はRPAが代替することで大幅に効率化できます。
これに対してAIは、膨大なデータを分析して予測や判断を行う場面で真価を発揮します。画像認識を使った製造現場での不良品検出、過去の販売データをもとにした需要予測、チャットボットによる自然な顧客対応など、非定型で複雑な状況に対応できるのが強みです。
このように、RPAとAIは対象とする業務の種類や活用の場面が大きく異なり、それぞれを適材適所で組み合わせることで、より高い効果を得られるようになります。
RPAとAIを組み合わせるメリット
RPAとAIは単独でも十分に効果を発揮しますが、両者を組み合わせることで自動化の範囲をさらに広げられます。RPAが得意とする定型業務と、AIが得意とするデータ分析や判断を掛け合わせれば、これまで人間でなければ対応できなかった複雑な業務まで効率化が可能になります。ここでは、代表的な組み合わせの事例をいくつか紹介し、それぞれがどのような成果を生むのかを具体的に見ていきましょう。
RPA×AI-OCRで紙帳票をデジタル化
紙の請求書や申込書、注文書などを処理する業務は、手入力による負担やミスが多く発生しがちです。ここにAI-OCR(光学文字認識)を活用すれば、手書き文字や印刷文字を高精度でデータ化できます。さらにRPAを組み合わせることで、読み取った情報を基幹システムや会計ソフトに自動入力し、担当者の作業時間を大幅に削減できます。紙媒体が多く残る業種にとって、AI-OCRとRPAの連携はデジタル化推進の大きな一歩となります。
RPA×対話型AIで顧客対応を効率化
顧客からの問い合わせ対応は、内容が多岐にわたり、担当者の負担が大きい業務です。対話型AIを導入すれば、一次対応として顧客の質問に自動で回答し、必要に応じて適切な情報を提供できます。さらにRPAを組み合わせることで、顧客情報の参照や社内システムへの入力などの処理を自動化でき、対応時間の短縮と顧客満足度の向上を両立できます。人間の担当者は、AIやRPAでは対応が難しい複雑な相談に集中できるため、業務全体の効率が高まります。
RPA×AIでマーケティングや需要予測を最適化
マーケティングや需要予測の領域では、大量の顧客データや市場データを迅速に分析する必要があります。AIは過去の販売実績や顧客行動から将来の需要を予測し、購買傾向を分析することに優れています。その結果をRPAが活用し、販促メールの自動配信や在庫管理システムへのデータ反映、レポート作成を行うことで、マーケティング活動全体を効率化できます。これにより、スピーディーかつ的確な施策立案が可能となり、競争力の強化につながります。
RPA×AIで製造ラインや人員配置を改善
製造業においては、設備稼働状況や生産データを分析して最適化を図ることが重要です。AIを活用すれば、生産ラインの稼働効率や不良率の傾向を把握し、最適な改善策を導き出せます。さらにRPAを組み合わせることで、その改善策をシステムに反映させたり、作業スケジュールや人員配置を自動的に調整したりすることが可能になります。これにより、現場の生産性向上だけでなく、人件費削減や残業削減などの効果も期待でき、企業全体の業務改革へとつながります。
RPA×AIの活用事例
RPAとAIの組み合わせは、多様な業界で導入が進んでいます。従来は人の手に頼らざるを得なかった複雑な処理や、大量データを扱う業務も、自動化によって効率化や精度向上を実現できるようになりました。ここでは、自治体・銀行・人材サービス業・流通小売といった具体的な分野での活用事例を紹介し、RPA×AIがどのように価値を生み出しているのかを見ていきます。
自治体における申請処理の効率化
自治体では住民からの申請や届出に関する処理が膨大で、職員の大きな負担となっています。AI-OCRを使えば紙の申請書から文字情報を高精度で読み取り、RPAが自動的に住民情報システムへ登録できます。これにより、従来数日かかっていた処理が数時間で完了し、住民へのサービス提供スピードも向上します。また、入力ミスの削減や職員の残業削減にもつながり、行政サービスの質を維持しながら業務効率を改善できます。
銀行での口座開設・審査業務の自動化
金融機関では、口座開設時の本人確認や審査業務に多くの時間と人手が必要です。AIを用いて提出書類の真偽や画像データの照合を行い、その結果をRPAがシステムへ反映することで、審査プロセスを自動化できます。これにより、申込から口座開設までのリードタイムを大幅に短縮でき、顧客体験の向上と同時に業務コストの削減が実現します。特に銀行のようなセキュリティ要件が高い業界においても、RPA×AIの導入は業務品質の向上と効率化の両立を可能にしています。
人材サービス業におけるマッチング精度向上
人材サービス業では、求職者のスキルや希望条件と企業の求人情報をいかに精度高くマッチングするかが重要です。AIは履歴書や職務経歴書を解析し、スキルや適性を評価することが可能です。その結果をもとにRPAが候補者リストを自動生成し、担当者に提示することで、マッチング精度とスピードを同時に高められます。これにより、人材紹介の成功率が上がるだけでなく、候補者と企業双方の満足度向上にも寄与します。競争が激しい業界において、RPA×AIは差別化の大きな武器となります。
流通・小売での需要予測と在庫管理
流通・小売業では、商品の需要予測と在庫管理が収益に直結します。AIは過去の販売実績や季節要因、地域特性などを分析して需要を予測し、その結果をRPAが在庫発注や棚卸計画に反映します。これにより、品切れや在庫過多といったリスクを軽減し、売上の最大化とコスト削減を両立できます。また、販促キャンペーンやセールのタイミングにも柔軟に対応でき、顧客満足度の向上にもつながります。現場スタッフの負担も軽減され、戦略的な店舗運営が可能になります。
RPA・AI導入時の課題と注意点
RPAやAIは業務効率化や生産性向上に大きな効果を発揮する一方で、導入・運用にあたってはいくつかの課題や注意点があります。事前にメリットだけでなくリスクや課題を理解しておくことで、よりスムーズかつ効果的な活用につなげることが可能です。ここでは、導入検討時に特に留意すべき3つのポイントを解説します。
導入コストとROIの見極め
RPAは比較的低コストで導入しやすいものの、対象業務の選定を誤れば十分な効果が得られない可能性があります。AIについては、学習データの整備やアルゴリズムの開発に多大なコストと時間がかかることが一般的です。そのため、導入に際しては初期費用だけでなく運用・保守にかかるコストも含めてROI(投資対効果)を試算することが重要です。短期的なコスト削減だけでなく、中長期的に見て業務効率化やサービス品質向上につながるかどうかを判断材料にする必要があります。
現場スタッフへの定着支援
RPAやAIを導入しただけでは業務効率化は定着しません。現場のスタッフが新しいツールを使いこなし、日常業務に組み込むことができるかが成否を分けます。そのためには、導入時の研修やマニュアル整備に加え、現場でのサポート体制を充実させることが不可欠です。また、業務プロセスの一部が自動化されることでスタッフの役割が変化する場合もあるため、モチベーション維持や適切な業務分担の再設計も必要になります。人とテクノロジーが共存できる環境を整えることが、長期的な定着につながります。
セキュリティ・ガバナンスの確保
RPAやAIはシステムやデータに直接アクセスして業務を行うため、セキュリティやガバナンスの観点でも十分な配慮が求められます。たとえば、個人情報や機密データを扱う場合には、アクセス権限の管理やログの監視が不可欠です。また、AIは学習データの偏りによる誤判断リスクがあり、RPAは誤設定や不正利用による業務停止リスクも存在します。こうしたリスクを最小限に抑えるためには、セキュリティポリシーや運用ルールを策定し、内部統制を徹底することが大切です。技術面だけでなく組織的な管理体制を整備することが、安心・安全な活用の前提となります。
ICはRPA×AI活用をサポートします

出典:システム開発のIC
RPAやAIを自社に導入しようと考えても、業務プロセスの可視化や自動化対象の選定、ツールの比較検討、導入後の運用体制構築など、多くの課題が立ちはだかります。特にRPAとAIを組み合わせて活用する場合、現場の業務フローを正しく理解したうえで最適なソリューションを選択することが重要です。
ICでは、こうした課題に対応するため、RPAとAIを活用したITソリューションを一貫してご提供しています。業務分析から設計、導入支援、現場スタッフ向けの研修や運用サポートまでトータルで支援するため、初めての導入でも安心です。すでに導入済みの企業に対しては、さらなる高度活用や効率化のアドバイザリーも行い、継続的な改善をサポートします。業務効率化やデジタル化を加速させたいとお考えの企業様は、ぜひICにご相談ください。
まとめ
RPAはルールに基づいた定型業務の自動化に強みを持ち、AIは大量データの分析や判断を得意とする技術です。両者を組み合わせることで、従来は困難だった複雑な業務や高度な意思決定の自動化が可能となり、業務効率化だけでなくサービス品質や競争力の向上にもつながります。
一方で、導入コストやROIの見極め、現場スタッフへの定着支援、セキュリティ・ガバナンスといった課題にも注意が必要です。こうした課題を克服し、最大限の成果を得るには、専門的な知見を持つパートナーとともに進めることが成功の近道となります。
ICは、RPAとAIの導入から運用支援まで幅広くサポートし、企業の業務変革を実現します。デジタル化の第一歩として、ぜひICのソリューションをご活用ください。
前の記事

APIとは?仕組み・メリット・活用事例までわかりやすく解説
次の記事

インフラ診断とは?目的・内容・流れ・料金相場までわかりやすく解説